 ユーラシア大陸・北アメリカ原産で世界中に広がっている帰化植物。日本には昭和初期に移入した。 茎はよく分枝し毛があり,少し褐色をおびる。刺のある果実をつけ,動物により運ばれる。畑などで害草として問題になっている。
ユーラシア大陸・北アメリカ原産で世界中に広がっている帰化植物。日本には昭和初期に移入した。 茎はよく分枝し毛があり,少し褐色をおびる。刺のある果実をつけ,動物により運ばれる。畑などで害草として問題になっている。
葉
広卵形の葉は3~5に浅く裂け,葉の縁には低いきょ歯がある。
花
雄花は茎の先につき,雌花は茎の節などに数個ずつつく。雄花序は両性花で構成されているが結実しない。2つの雌花はつぼ状の総苞につつまれている。
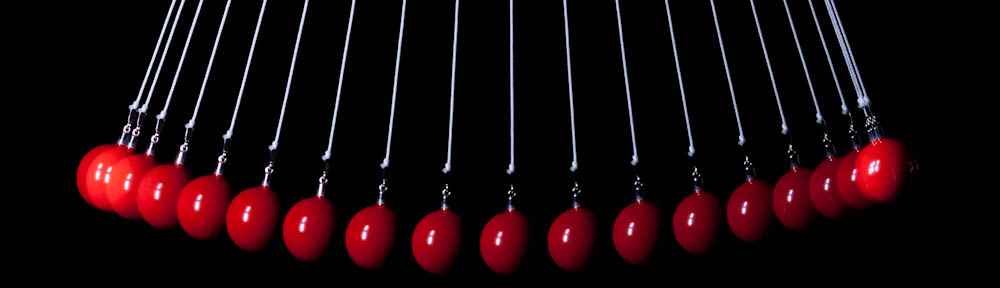
 ブラジル原産,日本には大正時代に移入した帰化植物で現在では本州以南の各地に広がっている。茎は直立し,表面に開出毛を密生する。茎の上部でまばらに分枝し,枝の先に多数頭花をつける。害草で畑に侵入されると駆除が難しい。
ブラジル原産,日本には大正時代に移入した帰化植物で現在では本州以南の各地に広がっている。茎は直立し,表面に開出毛を密生する。茎の上部でまばらに分枝し,枝の先に多数頭花をつける。害草で畑に侵入されると駆除が難しい。
葉は茎に多数つく。倒披針形で,下部の葉にはきょ歯があるが上部になるにつれてきょ歯がなくなる。葉柄も根生葉には長い柄があるが上部の葉にはほとんどない。両面に短毛がある。冬期は地面に葉をロゼット状に開く。
夏から秋に円錐花序を出し,多数の頭花をつける。頭花の舌状花は花弁が小さく,筒状花とともにほとんど総苞内にあって目立たない。
よく似たヒメムカシヨモギは舌状花弁が長く総包の外に出ていて見える。
 もとは南米原産で世界に広く帰化した植物。日本には明治中期にもちこまれ広まったが,近年減少している。全体に灰白色の毛が生えている。主軸は夏に花をつけた後成長を止めるが,その後側枝が伸び秋に花を咲かせるか枯れてしまう。側枝は主軸よりも高くなる。
もとは南米原産で世界に広く帰化した植物。日本には明治中期にもちこまれ広まったが,近年減少している。全体に灰白色の毛が生えている。主軸は夏に花をつけた後成長を止めるが,その後側枝が伸び秋に花を咲かせるか枯れてしまう。側枝は主軸よりも高くなる。
根生葉は羽状に深裂し,まばらで粗いきょ歯がある。茎生葉はきょ歯がほとんどなく,よじれるものもある。両面に軟毛が密生する。
茎の上部で分枝した枝の先に白い頭花を総状につける。頭花には雄花である白色の舌状花がたくさんあるが,小さく目立たない。両性花(管状花)は黄色で頭花の中央にある。主軸の花は夏に咲き,その後秋に側枝の花が咲く。
オオアレチノギクに比べて背丈が低く,頭花は大きい。
 北アメリカ原産で北半球に広く帰化している多年生草本。日本には明治時代に移入し,戦後に広まった。空き地や河原などに大きな群落を形成しているのをよく見かける。茎は直立し,高さは人の背をこえて2.5mに達する。葉と茎には短毛が密生する。 繁殖力が強く,種子からのみでなく地下茎を伸ばして増える。根から他の植物の生育をさまたげる物質をだすため,この植物が多い場所は他の植物がはえにくくなる。
北アメリカ原産で北半球に広く帰化している多年生草本。日本には明治時代に移入し,戦後に広まった。空き地や河原などに大きな群落を形成しているのをよく見かける。茎は直立し,高さは人の背をこえて2.5mに達する。葉と茎には短毛が密生する。 繁殖力が強く,種子からのみでなく地下茎を伸ばして増える。根から他の植物の生育をさまたげる物質をだすため,この植物が多い場所は他の植物がはえにくくなる。
先がとがった細長い楕円形の葉は密につき,互生する。縁には低いきょ歯がある。葉には短毛が生える。
茎の上部に多数の頭花からなる総状花序をを複数出し,全体として円錐状の花序を形成する。頭花は黄色の管状花と舌状花からなる。
よく似たオオアワダチソウは花期が夏で,茎や葉にはほとんど毛がない。