 中国河南省、安陽。1899年の発掘で「殷の都(BC1500-1100)」の存在が明らかになりました。
中国河南省、安陽。1899年の発掘で「殷の都(BC1500-1100)」の存在が明らかになりました。 おびただしい数の亀甲です。安陽、殷墟博物苑
おびただしい数の亀甲です。安陽、殷墟博物苑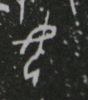
 甲骨に刻された「女」(殷代)
甲骨に刻された「女」(殷代)これから「女」という文字の変化をみていきます。

 中国最重の青銅器、司母戊鼎 安陽出土(殷代)
中国最重の青銅器、司母戊鼎 安陽出土(殷代)この頃は「女」「母」、両方の意で使われています。

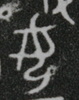 小子□卣 白鶴美術館 (殷代)
小子□卣 白鶴美術館 (殷代)「手を前に交え、裾を押さえて跪く姿」です。

 大盂鼎 北京国家博物館蔵 (BC1100年頃、西周初期)
大盂鼎 北京国家博物館蔵 (BC1100年頃、西周初期)
 彔□尊(西周初期)
彔□尊(西周初期)
 大克鼎 上海博物館蔵 (西周中期)
大克鼎 上海博物館蔵 (西周中期) 魯大司徒□ (BC720-220、東周)
魯大司徒□ (BC720-220、東周)
 石鼓 北京故宮博物院蔵 (BC374頃)
石鼓 北京故宮博物院蔵 (BC374頃)石刻では最古のもので、ここに「如」の字があります。

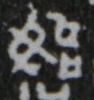 権量銘 (BC221、秦代)
権量銘 (BC221、秦代)始皇帝は度量衡の原器(青銅器、鉄器)を広く領布。
始皇帝の「始」の女偏の中心線が垂直から、斜めへと変化しています。

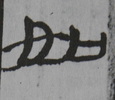 漢代木簡 (前漢末期)
漢代木簡 (前漢末期)
 元嘉元年画像石題 (AD151、漢代末)
元嘉元年画像石題 (AD151、漢代末)漢代(BC206−AD220)は横に広い形の隷書体の石刻が盛んとなり、青銅器は姿を消していきました。有名な碑の「女」をさがしてみます。
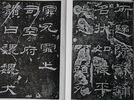
 乙英碑 (AD153、 後漢)
乙英碑 (AD153、 後漢)
 礼器碑 (AD156, 後漢)
礼器碑 (AD156, 後漢)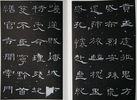
 曹全碑 (AD170, 後漢)
曹全碑 (AD170, 後漢)
 校官碑 (AD181, 後漢)
校官碑 (AD181, 後漢)
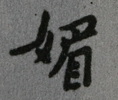 漢代末の行書体です。祭邑(AD133-192)
漢代末の行書体です。祭邑(AD133-192)
 漢代末の草書体です。張芝(−AD192)
漢代末の草書体です。張芝(−AD192)
 宣示表(鐘繇の楷書体です)
宣示表(鐘繇の楷書体です)−魏(AD151-230)

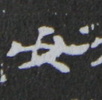 士孫松墓志(AD302−西晋)
士孫松墓志(AD302−西晋)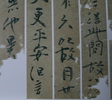
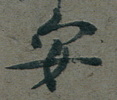 楼蘭出土残紙 (魏、晋)
楼蘭出土残紙 (魏、晋)紙に書かれた最古のもので、隷から移行期の
草、行、楷が見られます。

 諸物要集経(写経残巻)(AD296−西晋)
諸物要集経(写経残巻)(AD296−西晋)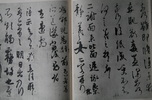
 書聖といわれる王羲之(321-379―東晋)の行書です。
書聖といわれる王羲之(321-379―東晋)の行書です。二謝帖、
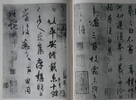
 奉橘帖
奉橘帖
 「安」の草書体(王羲之)長風帖
「安」の草書体(王羲之)長風帖
 洛神賦(王羲之の子の王献之、344-386)の楷書です。(東晋)
洛神賦(王羲之の子の王献之、344-386)の楷書です。(東晋)
 北海王妃墓志(AD510)
北海王妃墓志(AD510)北魏(AD386-535)には盛んに楷書細字の墓誌銘が作られました。

 張黒女墓志 (AD531−北魏)
張黒女墓志 (AD531−北魏)
 龍蔵寺碑 (AD586)
龍蔵寺碑 (AD586)隋代(581-618)にも墓誌が盛んです。
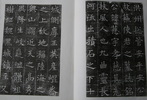
 蘇孝慈墓志 (603,隋)
蘇孝慈墓志 (603,隋)
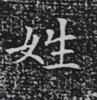 美人董氏墓志 (597,隋)
美人董氏墓志 (597,隋)
 蘇王華墓志銘 (欧陽詢,619)
蘇王華墓志銘 (欧陽詢,619)唐代(618-907)になると、隷書体は消えて、
完成された草、行、楷のオン パレードです。
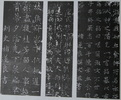
 隋清娯墓志銘 (褚遂良、651−唐)
隋清娯墓志銘 (褚遂良、651−唐)
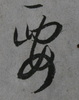 書譜 (孫過庭、648-703−唐)
書譜 (孫過庭、648-703−唐)
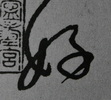 自叙帖 (懐素、737−?−唐)
自叙帖 (懐素、737−?−唐)
 孔子廟堂碑 (虞世南、626―唐)
孔子廟堂碑 (虞世南、626―唐)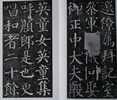
 顔勤礼碑 (顔真卿、779―唐)
顔勤礼碑 (顔真卿、779―唐)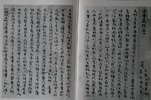
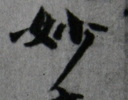 法華経義疏 (聖徳太子、615―飛鳥)現在残されている日本最古の書です。飛鳥、白鳳、奈良時代は仏教伝来と共に写経全盛で書き手は渡来人あり、日本人あり。百済を経由したもので、北魏、隋の墓志銘を書いています。
法華経義疏 (聖徳太子、615―飛鳥)現在残されている日本最古の書です。飛鳥、白鳳、奈良時代は仏教伝来と共に写経全盛で書き手は渡来人あり、日本人あり。百済を経由したもので、北魏、隋の墓志銘を書いています。
 紀吉継墓志 (飛鳥)
紀吉継墓志 (飛鳥)
 聖武天皇勅旨一切経(天平6年―734)
聖武天皇勅旨一切経(天平6年―734)
 光明皇后発願一切経(天平15年−743)
光明皇后発願一切経(天平15年−743)
 紺紙銀泥二月堂焼経
紺紙銀泥二月堂焼経
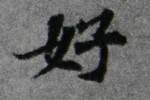 過去現在因果経
過去現在因果経
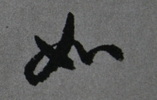 風信帖 (空海、774-835―平安初期) ☆三筆―空海、逸勢、嵯峨天皇
風信帖 (空海、774-835―平安初期) ☆三筆―空海、逸勢、嵯峨天皇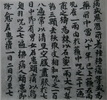
 (橘逸勢、778-?,―平安初期)
(橘逸勢、778-?,―平安初期)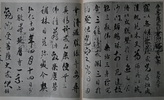
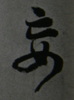 光定戒牒 (嵯峨天皇、−平安初期)
光定戒牒 (嵯峨天皇、−平安初期)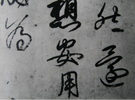
 屏風土代 (小野道風、896-966−平安中期)
屏風土代 (小野道風、896-966−平安中期)
 恩命帖 (藤原佐理、944-999―平安中期)
恩命帖 (藤原佐理、944-999―平安中期)
 白氏詩巻 (藤原行成、972-1027―平安中期)
白氏詩巻 (藤原行成、972-1027―平安中期)
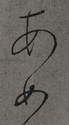 倭漢朗詠抄 (藤原公経、?-1099−平安中期)
倭漢朗詠抄 (藤原公経、?-1099−平安中期)